薬剤師になるには?基本的な流れや将来を見据えてやるべきことを解説
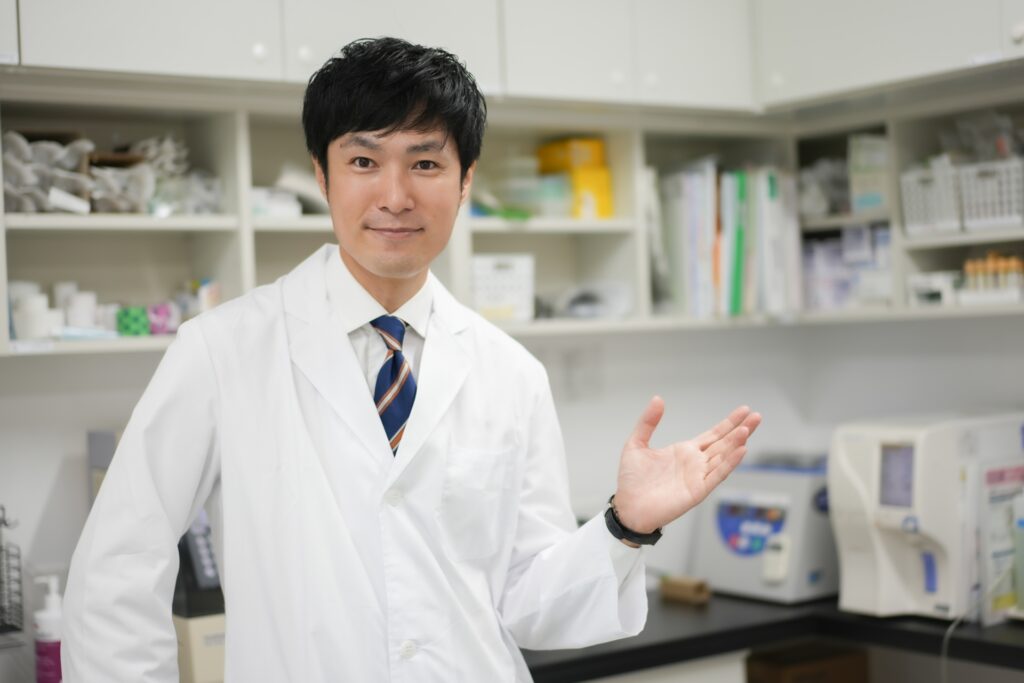
薬剤師は医療薬品全般の知識を持つ、薬のプロフェッショナルです。
医者が診断した薬を処方し、人々の健康を支える職業として広く認知されています。
その需要は今後も高まることが考えられるため、薬剤師を目指して勉強する人も増えています。
その際にはまず薬剤師になるにはどうすればいいのかを明確に、必要な行動を理解するのが重要です。
本記事では「薬剤師になるにはどうすればいい?」という基本と、将来に向けてやるべきことを解説します。
関連記事:薬剤師として働くやりがいとは?
やりがいを感じる瞬間やモチベーションが上がらないときの対処法を解説
薬剤師になるには?

薬剤師になるには、勉強をして必要なスキル・資格を取得する必要があります。
薬剤師になるためのルートは明確に決まっているため、就職を目指すのなら基本となる流れの把握が重要です。
以下では、薬剤師になるための基本的な流れを解説します。
6年制の薬学科を卒業する
薬剤師になるには、6年制の薬学科で薬剤師養成課程を修了したうえで、卒業することが条件です。
薬学部は2006年度に、これまで4年だった学習期間を6年に引き上げました。
これは医薬分野・技術の発展によって、4年間で十分な学習が難しくなったことが理由とされています。
社会の変化に対応するために、長期実習やアドバンスト教育が行える環境を整え、6年制への変化が進められました。
そのため、一般的な大学と違い、薬剤師を目指す際にプラスで2年間の学習期間が必要になります。
就職のタイミングも変わってくるため、人生設計を考えるうえで重要な2年間となるでしょう。
6年制の薬学科では、4年生のときに薬学共用試験を受けて、実務実習に必要な能力があるかチェックされます。
その後5年生で医療現場や薬局での実習を体験し、6年生で就職活動を進めるのが基本的な流れです。
4年制の薬科学科で学んでから大学院に進む
6年制の大学を卒業するのが薬剤師になる基本的な流れですが、2017年度までの入学者の場合、4年制の薬科学科で学んでから大学院に進み、実習と不足単位を取得することで薬剤師になれる条件を満たせます。
6年制の学習が一般的になった現在でも、研究者として働くことを目指す人向けに、4年制の薬科学科があります。
「研究者を目指して4年制の学科に入ったけれど、薬剤師にも興味が出てきた」という場合には、大学院に進学して必要な単位を取得する方法が考えられます。
一方で、4年制の薬科学科から薬剤師を目指す制度は、あくまで2017年度までの入学者を対象にした特例です。
現在は2018年度以降の入学者に対して同様の措置が取られる予定がないため、基本的には6年制の薬学科を卒業する必要があります。
薬剤師になるには国家試験の受験が必須
大学の卒業後には、薬剤師の国家試験を受験して合格する必要があります。
薬剤師の国家試験は年に1回実施され、時期は毎年2月となっています。
試験内容には「物理・化学・生物」「衛生」「薬理」「薬剤」「病態・薬物治療」「法規・制度・倫理」などがあり、必須問題が90問、薬学理論問題の一般問題が105問、薬学実践問題の一般問題が150問の合計345問で構成されています。
国家試験の合格基準は、「正答率が平均点と標準偏差を用いた相対基準を上回っている」「必須問題全体の正答率が70%以上で、さらに各科目の正答率が30%以上」「禁忌肢問題の選択数が2問以下」となっています。
昨今の合格率は60%台をキープしているため、きちんと時間をかけて対策すれば合格基準を超えることは難しくないでしょう。
関連記事:薬剤師の仕事内容をわかりやすく解説!
薬剤師になるために必要なこと

薬剤師になるためには、さまざまな準備や気持ちの整理が必要です。
事前にどれだけ準備ができたかで、薬剤師になるまでの流れが変わってくるでしょう。
以下では、薬剤師になるために必要なことを解説します。
自分に合った大学を選ぶ
薬剤師になるのなら、自分に合った大学を選ぶことが重要です。
薬剤師になるための薬剤師養成課程を学べる大学は、全国に多数あります。
しかし、各大学ごとに特徴や魅力は異なるため、自分に合わない学校を選択すると思うような勉強ができない可能性もあります。
最悪の場合には勉強のモチベーションが続かず、退学などの挫折を味わうケースもあるでしょう。
そのため薬剤師を目指す際には、慎重に大学を選ぶのがポイントです。
大学でしっかりと学ぶ意識を高める
薬剤師を目指す際には、大学でしっかりと学ぶ意識を高めておくことも重要です。
薬学部は学ぶことが多く、実習も含めて多くの学習経験が必要になります。
そのため日頃から勉強する意思を持ち、在学中にスキルアップできるように積極的に動くことが大切です。
大学生活には、楽しいことがたくさんあります。
周囲に目移りしてしまい、勉強に身が入らなくなることもあるでしょう。
しかし、薬剤師を目指すのなら大学生活を最大限に活用し、知識・技術の習得を目指す必要があります。
もちろん、勉強ばかりではなくリフレッシュも重要なので、ときには趣味や友人関係に時間を使うのも有効です。
進路について早めに考えておく
薬剤師が働ける職場は、増加傾向にあります。
そのため具体的な進路を早めに決めて、その職場で求められる能力を育んでおくのもポイントです。
就職先次第で薬剤師に求められる役割や仕事内容が変わるケースもあるので、業界研究などに時間を使うことも重要です。
自分に向いている職場、興味の持てる業界をチェックして、最適な進路を選べるように備えるとよいでしょう。
大学のキャリアセンターなどを利用することで、就職の相談や企業研究のサポートが受けられます。
自分だけで就職活動をするのが難しいと感じるときには、大学のサービスを積極的に活用するのもおすすめです。
関連記事:薬剤師のキャリアアップに関わる資格とは|おすすめの補助資格を紹介
まとめ
薬剤師になるには、6年制の薬学科で薬剤師養成課程を修了し、薬剤師の国家試験に合格する必要があります。
大学進学と国家試験の合格が欠かせないため、受験に向けた早めの準備が重要です。
薬剤師を目指すと決めたのなら、まず進路を決めて、必要な行動に移していくとよいでしょう。
薬剤師になるのなら、「横浜薬科大学」への進学がおすすめです。
「横浜薬科大学」ではさまざまな授業を通して、幅広い薬学分野をカバーできる人材の育成を実施しています。
患者中心の医療を実現することを目的とし、健康・漢方・臨床という3つの6年制学科を設置しているのが特徴です。
自身の興味関心に合わせて学科を選べるため、学習モチベーションを継続しやすいでしょう。
この機会に「横浜薬科大学」の特徴をチェックし、本格的に薬剤師になるための準備を進めてみてはいかがでしょうか。




